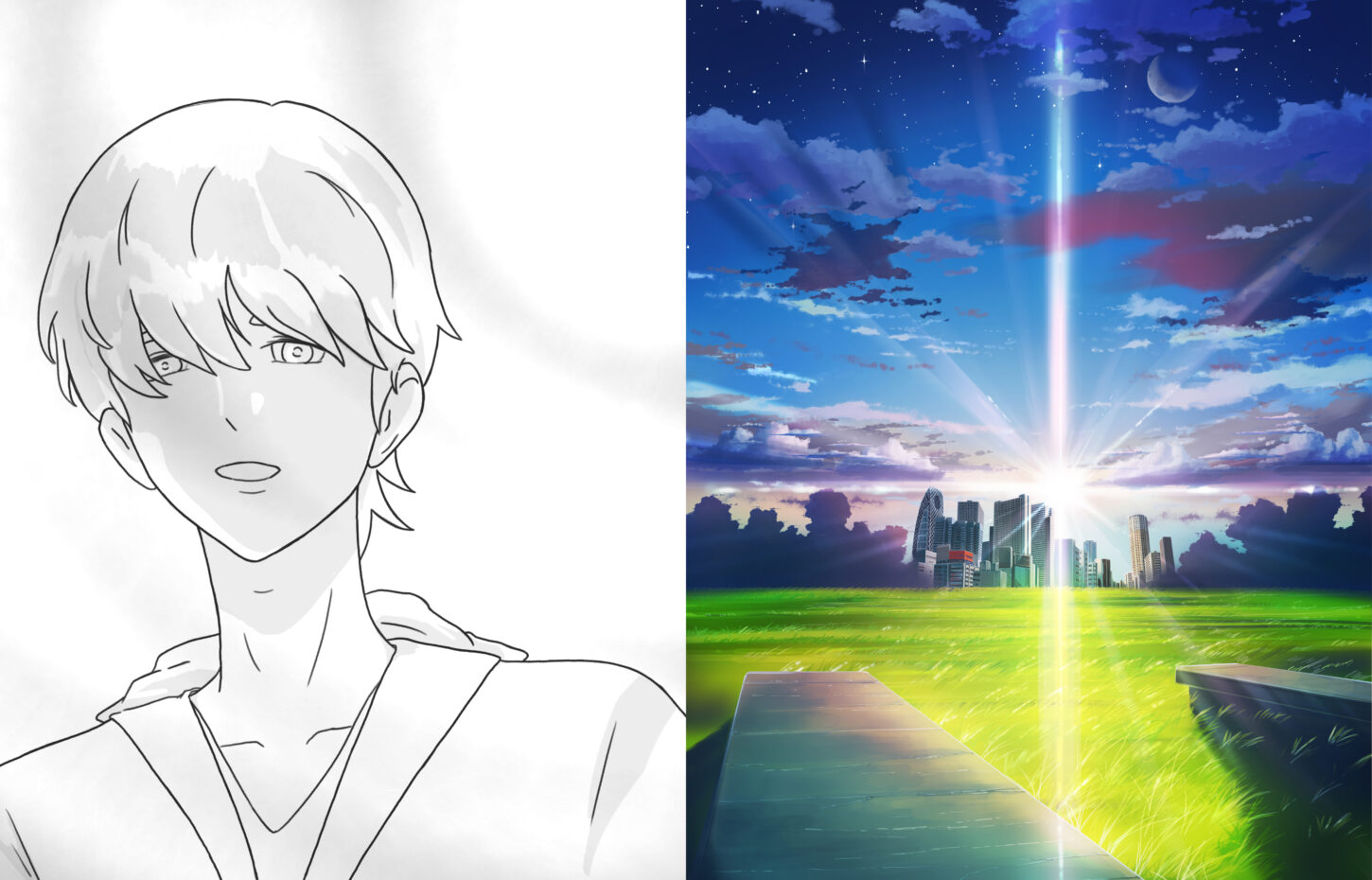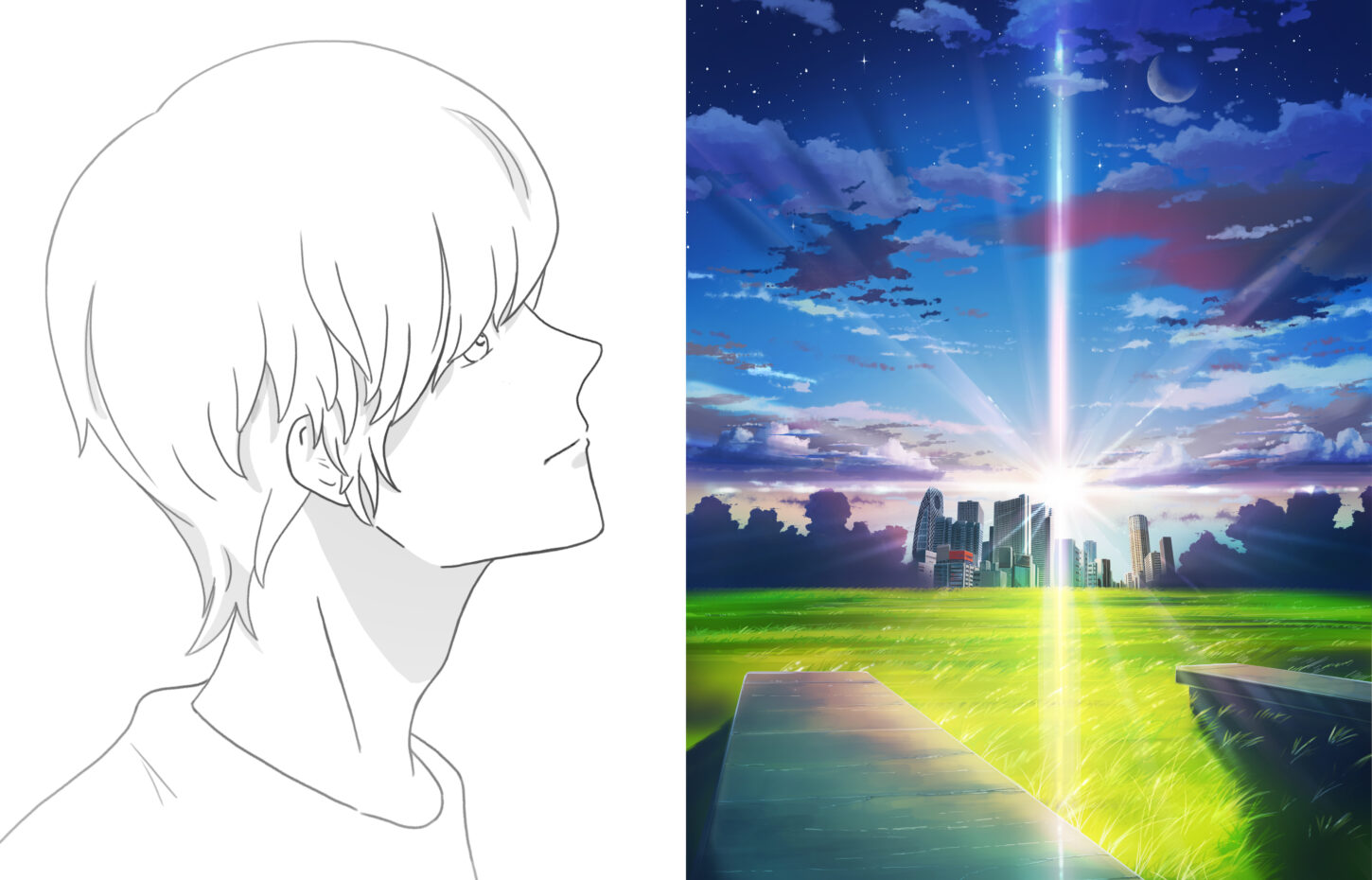第24回 窓に映るこっちと車外。

表示された名前を一瞥して特にためらいも覚えずに画面をスライドし、スピーカーをオンにする。
『もしもし陽向? 違う、違うよ。ごめんなさい』
何回かひなたさんと寝たことがある。
枯れ葉が積もりはじめるころまで、ときどき真夜中に「やっぱり眠れない」と送ってきたひなたさんを、わたしは部屋に招いていた。
小さくつけた灯だけでもわかるほどばつが悪そうに立っていて、めくった毛布のなかにそっと腕を引くと、されるがままベッドに入る。
「……狭い」
身を寄せながら文句を垂れる人に、あくびをかみ殺しながら言った。
「わたしも狭い」
「……ごめん」
「いいよ」
時計の針の音しかしない世界にうつらうつらしていた。肋骨と肋骨の間がずきずきしているのも、熱に浮かされたように焦点が定まらないのも、苦痛とは違う別のものだった。
「同時に死にたいなって思ってたんだよね」
そう言い、右を下にしてごそごそとわたしのほうを向きながら、ひなたさんは息を吐いた。
「美沙は滅多に傷つかないし、次の日には忘れるとか言ってるけどさぁ……案外怖いもの知らずだから、あの人」
あの人、と、ひなたさんは努めてぶっきらぼうに彼女を指した。だからさぁ。締まりのない声が続く。
「美沙より長生きしなきゃって思ってたんだぁ。でもたぶん美沙のが丈夫だし、あたしだって美沙がいないのはやだし……みんなと時間軸が違って世界がずれて、特別に早く、なんでもへっちゃらな強い大人になれると思ってた。でもそんなことなかった。手をつないでスーパーに行ったり、一緒にお弁当食べたり、したかった」
群衆のひとりとして出会っていたら、その辺を歩いている恋人同士のように振る舞い、ときたま性別をスパイスに身体じゅうの血液を熱く沸騰させていたのだろうと悟る。わたしは深呼吸をした。ため息じゃなくて。
「ひなたさんさ」
「ん?」
「なんでそんな顔してるの」
見えない口角に手探りで触れてみる。
「あと五分で世界が終わるみたいな」
親指と人さし指の間にぽつりと落ちてくる。ほらまたすぐ泣くんだから。
どうせ世界は終わらないのに。
その上シャッターを切るたびに自分をさらけ出してしまうから、痛くて痛くてたまらないのだ。皮を剥がれて神経と内臓を直にざらざらとこすられているのだ。
「残り五分で世界が終わるって言われたら、ひなたさんは何したい?」
「……五分? 無理でしょ。何もできないって」
「ほら早く。考えてる間に終わるよ」
「はぁ? 待って、じゃあ……」
数秒考えて、ひなたさんは答えにくそうに枕に顔を押しつけた。こういうときのひなたさんには怯んでしまう。ただでさえ眠いんだから。
「……とりあえず美沙に電話する。出てもらえたら五分話す。だめだったら……日当たりのいいところで昼寝する」
「で、そのまま?」
「そう、そのまま」
そう。よかった。
身体の向きを変えて腕の間に忍びこむ。
「ちょっと何してんの純」
「抱き枕ほしいでしょ? 髪質はたいして変わらないよ。あそこまで痩せてないけど」
重い、には重いで返してあげる。
「意味わかんねー……」とひなたさんは腕に力をこめた。
まどろんでいるのはたしかにわたしだった。淳ではなくわたしが祈っていた。ふたりの道が結ばれる夢を。
伊月美沙は沈黙を確認すると、焦ったように続けた。
『陽向はなんでもわかってくれるけど、言わなきゃいけないこととか、言っちゃいけないこともあるんだよね。私、どこかで勝手に思ってたのかも。私のためなら陽向は傷ついても大丈夫なんだって。そんなわけないのにね。最低だね』
ごめんね、ごめんね、と繰り返す。いつまで雰囲気づくりに勤しんでいるつもりだろう。一方的な夢想と現実の区別がつかなくなっていよいよ声を交わしたのに、お互いがひとりで踊っている。まどろっこしい。わたしはそれに付き合いたい。
『陽向、怒ってよ。私が苦しくなるくらい怒ってよ。やきもちとか、美沙は無理しすぎだとか、あたしを置いていくなーとかさ……陽向は……私が嬉しくなる怒り方しかしてくれないじゃん』
いまだってさ、と伊月美沙は言う。
『電話くれたのが、すっごい、すっごいね……』
ごーごーと音がして乱れる声を消し飛ばそうとする。わたしは何も答えずにひなたさんのふりをしていた。電話越しの声にはアナウンスが混ざっている。
『……追いかければよかった。陽向が置いていってくれたものを踏みにじってでも、ついていけばよかった』
ねぇ陽向。私さ、どうしてあなたの言う大人だったんだろう。
遠くで、悲鳴のような鳥の鳴き声が跳ね返った。
じゃあそろそろ入りだから。という諦めたような言葉の合間を縫う機械的な声のなかに、普通列車が入ることを知らせる内容を捕まえる。行き先は新幹線が停まる連絡駅。かすかに波が打ちつけている。
ふたりはずるい奇跡など持ってはいなかった。
『ばいばい、陽向……』
「……待って」
駅へと走り、伊月美沙がいなくならないことを祈りつつ電車に飛び乗った。わたしは、これで淳と別れよう、と思いながら、先頭の車両のいちばん前の角に立った。窓に映るこっちと車外、混ざって世界がわからなくなった。淳、あなたに死ねと言いたかった。
まっすぐな脚が、ごつごつした浜辺のまだ冷たい石を直に踏んでいた。
「凍死するよ、おねーさん」
©︎Nanako Otake / Studio AOIKARA