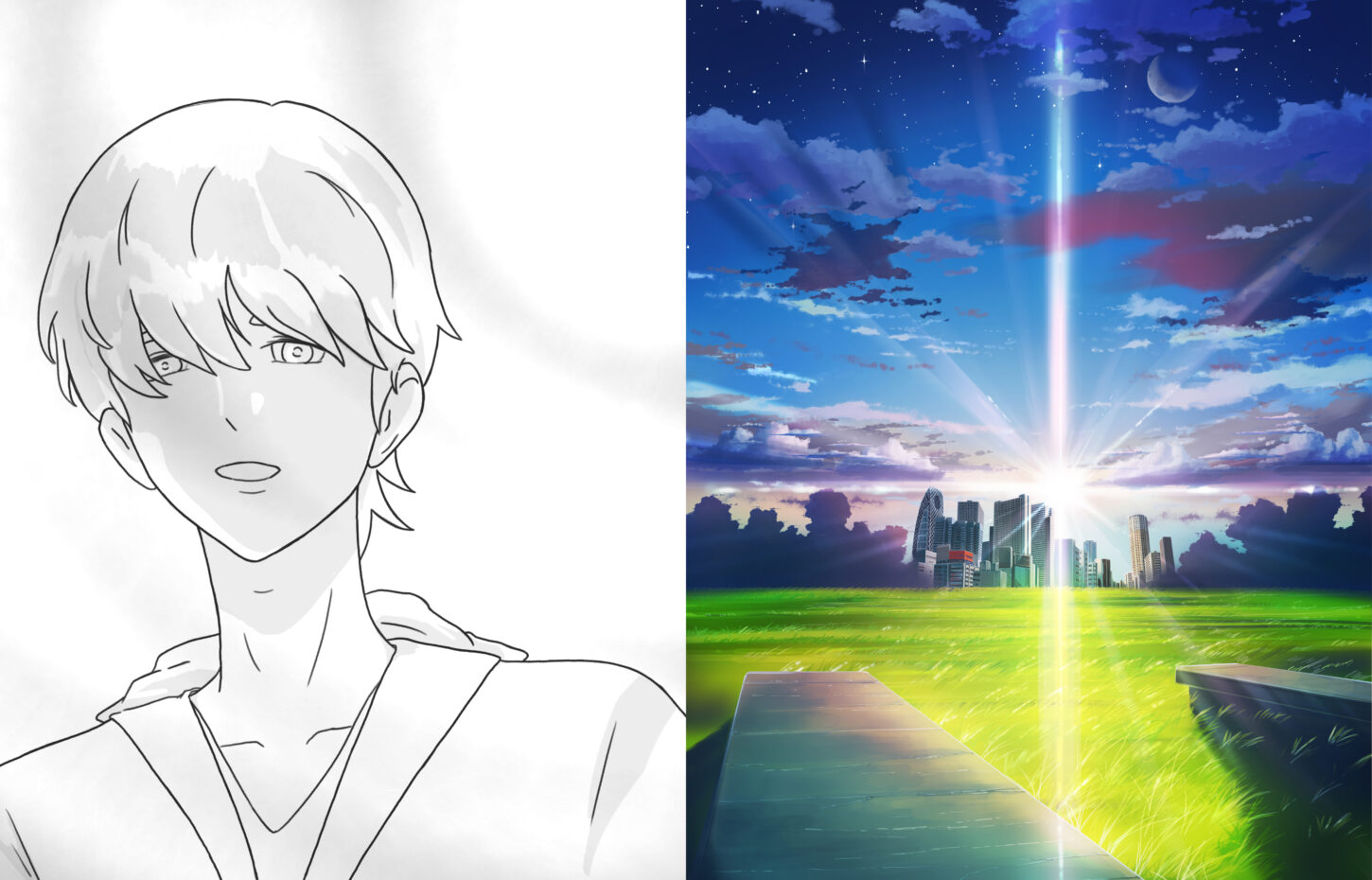第19回 若竹色。

6
さわやかなくるしいきもちに、なれたよやっと。
7
あたしは当てもなく歩き続けた。数時間か、数日か、洗える場所を探してさまよっていた。
いつしかあたしは、とめどない流れを見つけていた。海のように追憶させてはくれない。だったら、と思って腰まで浸かり自分の手で身体を引っかいた。なのに、何ひとつ削られないままべっとりと、その上ますますなすりつけられている。
砕けそう。こんなにやっても、あたしはまだ汚い。よごれが目に見えちゃう前にぜんぶなくすの。どれだけ冷たくったって、きっともっと深いところに行かなきゃいけないんだ。
ほとんど、衝動。何かに引っ張られたみたいに前のめりになる。水が口に入って咳きこんで、沈んで、そのまま仰向けに——
「陽向!」
名前を、呼ばれる。引っ張り上げられる感じがして、川底に足をつけた。ねぇ、なんで。
「やめてよ陽向」
美沙が、困っていた。だけど、あたしも困っている。綺麗な手が、あたしの手を握っていた。こんなにべたついているんだから、だめ。なのに。
「行くよ。おいで」
そう言った美沙の手を振りほどく。ぴしっと音がして、水が跳ねた。美沙は言いづらそうに顔をしかめて、陽向、とだけつぶやく。懸命に落ち着こうとしていた。その目に凝っているのは、失望、だったんじゃないの。
「美沙、何してんの。寒いでしょ」
「それは陽向もじゃん」
「そーゆー問題じゃないの、あたしは」
顔を背けると、美沙はなんにも言わなかった。だけど、どうにかして美沙をあったかいところに帰さなきゃ、と思っていくら考えようとしても、ちっとも集中できない。だって美沙がまた、指を絡めてくるから。冷え性でどんどんひんやりしていきながら、捕まえたからね、と言うみたいに、ぎゅっと。
「ねぇ」
そのせいで、思わず目を合わせてしまう。そしてすぐに、うそ、と思った。
あたしが再び「ミサ」と呼んだ日、その目からはふたつだけ、涙がこぼれた。あれ以来、美沙が泣くところを、あたしは見たことがない。
三滴めは、透明なオレンジだった。
触れられても、もう拒むことができない。気づけば水は濁っていて藻の匂い。ぬめっとしているはずなのに、それで濡れているのが美沙の手ならば少しも不快じゃなかった。美沙はあたしの頬をさすってから髪をくしゃっとやわらかく掴んで、毛先まで下ろして首に添える。ぴちゃぴちゃ、と数滴、川面を震わせた。
「……もう知ってるよ」
わかんないわけないじゃん、と続ける美沙の言葉はもっともだった。気がついてほしいと思ったことがないなんて真っ赤な嘘。
ほら、こんなさ、図々しいんだ。
「余計なことで悩んでないで……陽向はずっと、美沙ー美沙ーって……」
言ってればいいよ。と発したのだと思う。前と変わらず落ち着いた、さらりとしているのに耳に残る、途中で大きく跳ね返る声が飛んできて詰まって、窒息しそうになる。
「でもさっき……」
「……うるさいなぁ」
陽射しが川に反射して、美沙の顔の上で波が揺れ光っていた。
「……ごめん、嘘言った」
あいつが私のアレを撮るって言うから、事務所にも黙って消したの。あんな奴に見せるなんて悔しい。って。
「陽向にしか触らせてあげない」
それからふと我に返ったように目をそらした美沙の頬が、ぽーっと赤くなった。
うそだな。じゃなきゃ、大ばかものだ。目玉の裏側からぎゅうっとなる。それがつくり話だとしても、あたしに許されるための嘘ならば。真実であるのと変わらず細胞は沸騰する。
「ばかなの?」
「ばかは陽向でしょ」
「そうやって、びびりのくせにさ」
「もう……陽向が向こう見ずだからそう思うんじゃない?」
美沙の下まぶたが持ち上げられて声が裏返って、笑った。
いつだって、許してくれるのは美沙のほう。あたしが、空気を塗り替えて、うららかと言うにはあまりにもとっ散らかったスクランブルエッグみたいな世界を、その瞳に透写することを。
気持ち、を、なまえ、を、触りながら降りてくる、まなざし。
いつもいつも、交互に出てくる足を目で追いながら歩いていた。
探してもいいの?
目の前にいるじゃん。
ね、ばかだね。
「みっちゃんまた口のはしっこぴくぴくしてる、素直じゃないなぁ」
「ねぇほんと黙って。動くたびに貧乳の下着が透けてて笑っちゃいそう」
「そっくりそのまま返したいけど、いまそれすっごいいじりづらい……」
おっぱい丸出しになったことのほうが大事件なのに。ねぇ美沙。ごめんね。甘えたくって、ここまで来てくれたんだよね。
なぁんだ、って、高校生のときみたいにへらへらしてあげるのも、違うんだろうなぁ、と思った。あたしは涙を拭おうとしている美沙の手を掴む。
「待って。陽向の」
はっとしたように向けられた瞳に吸いこまれたなんてあとづけ。沈黙だけで察した美沙が目をとじると、もうひとつこぼれそうにまつげの間をきらりと揺れた。ゆっくり近づけば、むくんだ目の下側を黒くしているのはこすれたアイラインだけじゃない。そっか、人さし指のつけ根が少しぱりぱりしていた。あたしがこんなふうにさせちゃったのかなぁ。そっとくちびるでまぶたに触れると、その一滴が落ちて、隙間がじわじわ熱くなる。ちゃんと、しょっぱい。心がたまらなくとろけては息苦しい。美沙が、いる。
いま、もしカメラを持っていたとしても、あたしはきっと撮らないことを選ぶ。
いったん離れてからおでこを合わせると、美沙の目はかすかにざらついていたさっきよりもなめらかに潤む。ふふ、と笑う美沙の冷たい鼻とぶつかった。細くて繊細な髪が湿っていて、呼吸の震えが寒そうで。あたしも出るから、行こう。とは、言わせてもらえなかった。
「だめ。私も陽向になる」
森林の香りの柔軟剤。水没した腕時計が止まる。ふたりの息は浅い。今日、吸ってないんだ。吸ってないよ。隠さなくてもよかったんだよ、ほんとはだめだけど、そしたらもっと自然にそばにいられた。違うよ、吸ってるのを内緒にするつもりはなかった、ただ——
「……陽向の肺が汚れる」
あたしの肩に顔を埋めた美沙が、ずぴ、と鼻をすする。ごめん、寒いよね。と言うと、投げ返される強がり。おとなしく、あたしにおんぶされろ。
岸に向かいながら思い出していた。
青を漂っていた筏は、美沙を乗せてゆっくりと戻ってくる。カメラを置いて水にいっぽ足を入れると思ったよりひやっとしていて、あたしはそのまま浅瀬に進んだ。
「陽向、何やってんの?」
「だって、足冷えてると眠れないんでしょ?」
「……もう」
背を向けて、ほら、と促すと、美沙は諦めたように身体を預ける。身長に対しては足りないもののちゃんと重みはあった。細すぎるからもっと食べろなんて美沙には言ってはいけなくて、なら今日の晩ごはんは何がいいと言おうか、その瞬間も考えていた。息切れがぜったいにばれないように、黙って、ひとつひとつ踏み出す。
いま、そのときと同じように背中に美沙を感じて、あ、と思った。おんなじ、だった。あたしのも、背中に伝わる美沙のそれも、いつのまにか変わらない速さで重なって、いっこになる。
指に引っかけた美沙の靴と、前髪がはりつくあたしの顎と、左肩に力なく乗っかる頭から、ぽつりぽつりと、犬の足跡みたいにしたたり落ちた。
「ひなた……」
「ん。いいよ、みさ」
樋門の柵にかかっていた群青のウィンドブレーカーに気づいて手探りで美沙にかぶせ、寝息に耳を澄ましながら、静かに裸足でアスファルトを踏んだ。
©︎Nanako Otake / Studio AOIKARA