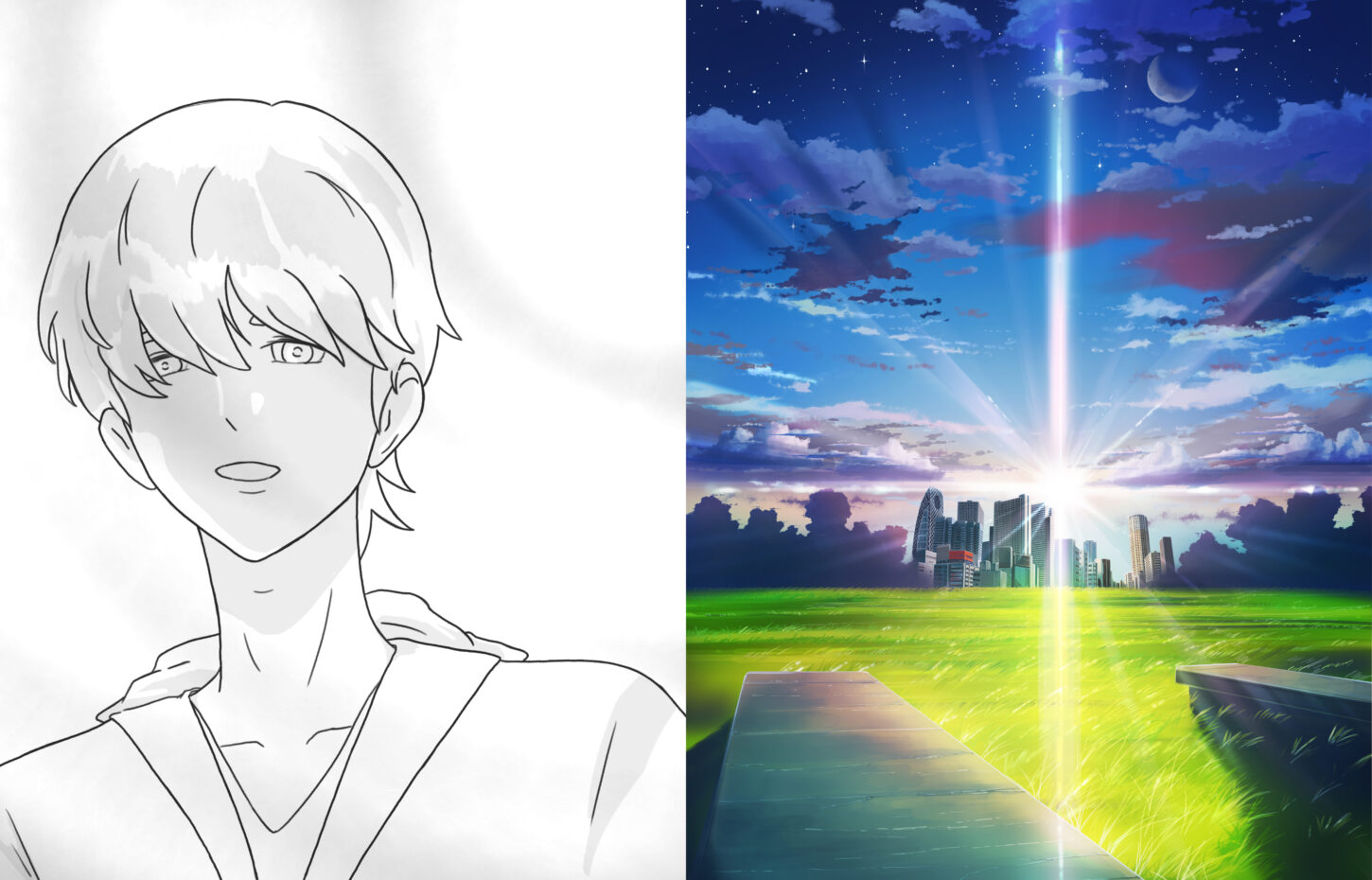第2回 うそばっかり。

「あおいろ」 芳川 陽向
1
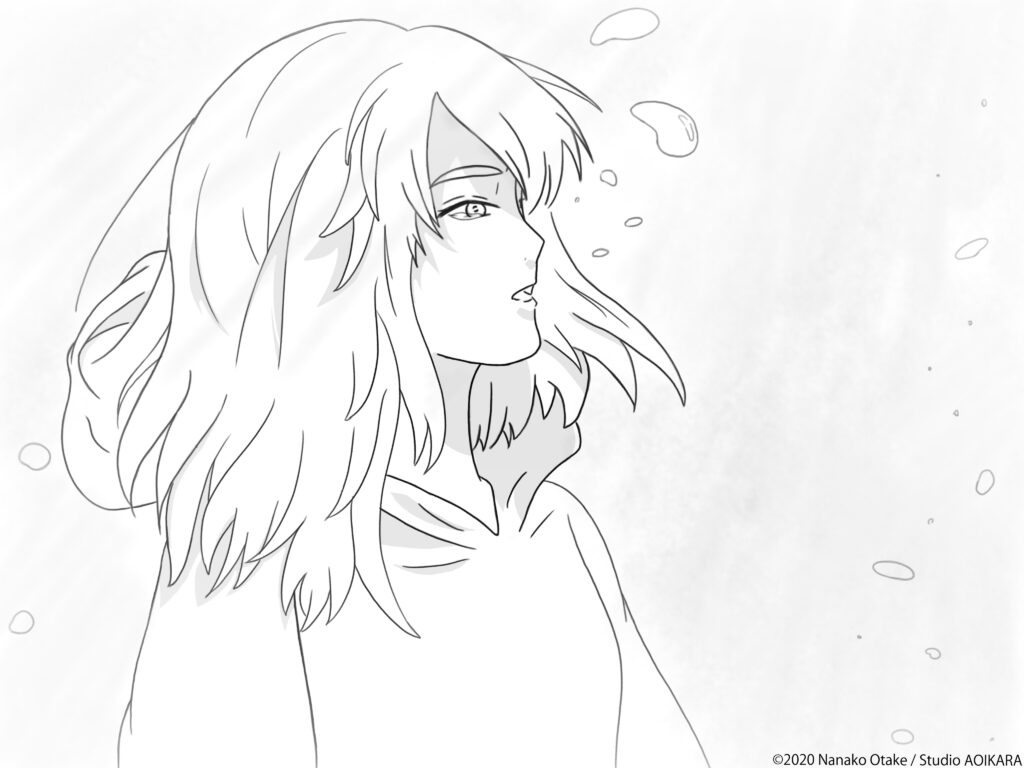
あたしのたくらみは無言でふくらみ、破けてトマトの汁のような匂いを振りまく。
じわりじわりと上がってくる真っ黒な水は、もう肩に届いてしまった。輝くような恐怖に浸けられて、喜びがほとばしっては身体が熱くなる。コトコトと止まらない動悸に、ぶつ切りにされちゃいそう。
絡んでいた誰かの手を引っぱって、酸素を与えようと抱き上げた。瞬間、掴まれた頭の骨は砕けそうに、鼻先まで水面下に沈む。そうしてください、とこぼれた声は泡になってゆらゆらと遠ざかっていった。深く横たわってしまうと、水はガラスに藻が張ったみたいなまばらな緑。息はうまく吸えないのに、磯臭い。
どうしよう、どうしよう、えぐられる。
この水のなかには、わずかに人が吸える空気があるのか。はーっ、はーっ、という息づかいがこだましていた。あたしはこれが夢だということをわかっている。それなのに、かみそりで肌をなぞられた感じがして、果てそうでたまんない。抱きしめていた彼女は薄らぐ間もなく消えている。ここに来るまで浴びていた光線がとざされて一こまのフィルムに固定されてしまえば、遡ることもできない。
吸えるものを失ってぎゅっと目をとじると、まぶたの裏に、遠くが波打つのが見えた。
誰か、いる。
ゆれる人影。助けてよと手をのばして——
「ねぇ」
懐かしい声に鳥肌が立って目をひらいた。一気に視界がひらける。酸欠になった金魚みたいに水面を掴んだ。黄昏ゆく空が、視線の先でにじむ。周囲が白く光り——
すうっと引きこまれるように、目をあけた。
静寂のなかに、秒針の音を聞く。
「ねぇ陽向、私が死ぬところまで撮ってよね」
寝起きの頭に、聞こえた気がした。あぁ、そっか。
スマホを覚醒させると夜の八時を過ぎていて手が萎える。明るい時間は、起きてらんない。あたしが消えても回っている世界を、見ていたくない。むくりと起き上がり、掛け布団を蹴っ飛ばした。
三ぶんの一ほど残ったペットボトルの中身を飲み干して、海綿状になった頭に水分を含ませる。よろけながらスマホと財布だけを持ってドアノブを握ると、ひやりとした感覚もつかのま、ひらいた途端にもわっとした夏の最後の暗い熱気が侵入してきた。そろそろと歩いて階下の玄関を目指す。途中、おじいちゃんの部屋からひとりごとが聞こえるのはいつものこと。野球中継を観て本気で応援していた明るい声が聞こえなくなったのは、いつからだったか。
それもぜんぶ、あたしのせい。
ばたん、という重い響きとともに、家全体がきしんだ気がした。背を向けてゆっくりと歩きだしたあたしは、暗さのすきまに哀れっぽく点滅する街灯の間を縫うように進む。
誰かに。誰かに声を聞いてほしい。

ふらふらさまよい歩いていたら、コンビニが口をあけて待っていた。ぼんやりとした光に吸いこまれるようになかに入れば、嫌でも目に入る。ファッション誌の表紙でひとり、口元にやさしくも涼しげな形をたたえている伊月美沙。何もしなくたってさらさらでクセがない髪のつやも、静かな表情の浮かべ方も、あたしが手を離したくらいじゃ変わんない。よかった。と思えなくなってきたのが最近。だってなんか、顔が変わった。カラコンでかすぎ。涙ぶくろ、塗りすぎ。
美沙は美沙のいちばんかわいいところを、自分ひとりでは認められないんだ。だから誰かがそばで、うっとうしいくらいに褒めてあげなきゃいけないわけ。
「ねぇ」
紙の上の美沙が笑う。見ていると耳の奥がどくどくと鳴りはじめて、どこからかあふれてくるものをぜんぶ包みこんだかたまりを、つばと一緒に胸の奥へごくりと押し戻した。
なんでだろ。目の前がぼやけてくる。夢じゃないのに息ができない。だめだ、逃げたい。
気づけば走りだしていた。
息を切らしながら思い出す。美沙はいつだって水底の真んなかに足をつけて立っていた。だからどこでも息をすることができるあたしが代わりに空気を吸って、人工呼吸をするように口づけていた。美沙の欺瞞は硬くて重いけれどその一枚だけで、それさえ時間をかけてめくってあげればあたしはやわらかな頬に触れられた。
目の前に公園が見えたのに、すごく遠くにあるような気がした。世界がゆれて、地べたに腰を落としそうになる。もう、なんにも見えない。きらきらしたものを見つけるのが得意。これはいちばんの自慢なの。目と、耳と、鼻が、めっちゃいいの。そう言っていたあのころとは比べものになんないくらい、視界がとじる。
なんとか身体を引きずって、路地の脇に身を沈めた。
両手で顔を覆い、すーはー、すーはー、とゆっくり呼吸する。酸素が入ってきて、感覚が戻りはじめる。サンダルのすきまから触れる草が気持ち悪い。ぶーん、と音がして夜の山手通りを思い出したところで、口答えしているのは虫の羽音でしかなかった。耳の奥が、きんと痛む。このままあたしもどろどろに溶けだして、べっとりと夜の一部になってしまえるんだろうか。
「ねぇ、陽向」
ひなた、の、三文字が。気だるげな音でこだまする。
美沙の手をそっと握るのは、カメラを手に取る感覚と一緒だ。触れようとするたびにくらくらさせられ、ときどき安らかに裏切られる。裸眼はレンジファインダーよりももっと、しぶき上げる光と諧調の豊富な黒を見せた。そうして残った一瞬が、ずっと奥へとあたしを呼ぶ。どこまでもどこまでも。
冷静になって頭が冴えてくると、うるさい、と桜を仰ぎながら頬にぽっと同じ色を落とす美沙が浮かんだ。たばこの火を押しつけられたみたいに胸の皮の裏がひりつく。涙も出なくなっちゃった。代わりに、乾いたうめき声が漏れる。
「私が死ぬところまで撮ってよね」
あたしって、うそ。ばっかり。
くわん、と何かがぶつかる音。滑り降りる金属音。草がふさっと鳴く。
こんな夜に遊びにくる子どもなんかいない。不審者か、それともあたしのことが許せない誰かか。
どうでもいいんだよ。もう、どうなったって。
「ねぇ」
すぐそこまで来ていた足音が止まったと思ったら。あれ、声が若い。と、同時に知る。大好きだったあの一声は、ほかの人が発すると、こういう音がするんだ。
月がまぶしいなんて言い訳だった。
「どうしたの? さっきからなんか、つらそうだけど」
家と田んぼしかない街の新月では、くちびるの色もわからない。声を聞いて、たぶん、ちょっと年下なんだろうな、と思った。右足が、バスパンからむき出しになっている反対のふくらはぎを掻いて、またもとどおり地面を支える。つっかけたサンダルを、かかとがぺちっと、弾く。
わずかに角度が変わって薄暗い電灯がかぶさると、まるっこい大きな目が、ガラス玉みたいに白く光った。
はんぶん眠ったように「彼」をぼんやりと眺めていたら、一度もつらいと言った覚えがない気が、かすめる。
「何かあったの?」
「……まぁ」
「へぇ、グミいる?」
「……いらない」
あっそ、と、「彼」はウィンドブレーカーのポケットから手のひらサイズの袋を引っこ抜いた。ぺりぺりと音がして、虫歯のできそうな甘い香りが逃げ出す。これ、レモンだな。
「お疲れさまぁ」
土やら砂やらで摩擦されたあたしに構わず、「彼」はとなりに腰掛けた。知らない男子と並んで路上に座ってる、十九歳、えー、六か月の、昼夜逆転女。うん、まぁこれは。まともじゃ、ない。
グミをしまいながら、「彼」が言う。
「帰らなくていいの?」
「帰りたくない」
「ふーん」
帰ったって話し相手はいないし、外にいれば、誰かに会えるかもしんないし。ぼそぼそと言った声は届くことなく聞き返されて、そしたらあたしは「なんでもない」と答えるはずだった。
「誰かって、誰?」
この子の耳がいいのか、思った以上にあたしが、伝わってほしいなんて欲ばりなひらめきをしてしまったのか。
「別に誰でも」
握った拳の内側に爪が食いこんで熱くなる。手がのびてくることに、遠くを見て気がつかないふりをしていた。だけどやっぱり。そっと二度頭に触れて、軽く動かされる。心地よさに、思わず目をとじちゃいたくなる。
「じゃあ、いてあげる」
あたしはできるだけいい画質で「彼」を視界に捉えようとした。まだにごってはいるものの、目の裏の神経がぴきりと動く。やわらかな声が彷彿させるのは、素直な笑顔だった。
「一緒にいてあげる」
おしまいだ。そう思った。
薄い緑の芝生の先、滑り台の黄色。小さな山を貫くトンネルの赤と、青と。
また、見えはじめてしまう。

第3回:2020年9月19日(土) 12:00 公開予定
©︎2020 Nanako Otake / Studio AOIKARA