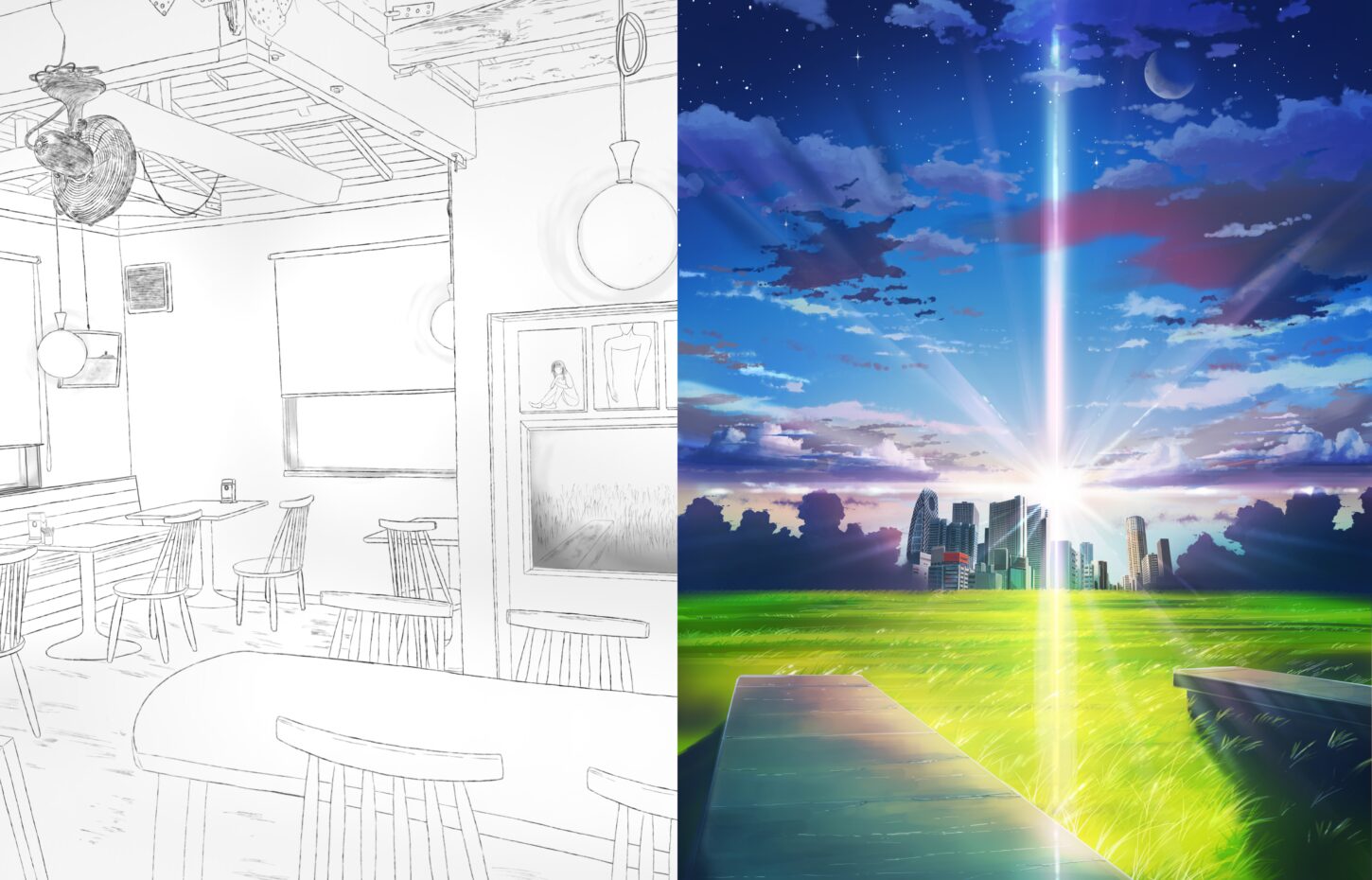第13回 気づいていた。

自分の環境に特別なこだわりを抱いたことはなかった。女の形をしているから女湯に入り、この顔だからこの表情を選ぶ。
駅の待合室に着いてガラス戸を引くとそこには空色のダッフルコートを着た雨谷真奈だけがいて、わたしに気づけばほわっと頬をゆるめる。
「ごめん、待った?」
「ううん、いま来たところだよ」
暖房が効いている割に赤く染まっている手を見て、自販機でお茶をふたつ買ってからとなりに座った。
渡す前にキャップをゆるめると、その凹凸にかじかんだ左手をこすられる。脇に挟んでいるのが億劫だったファッション誌の最新号は雨谷真奈の膝の上に返した。
「それ、ありがとう」
「また見たいのあったら言ってね。美沙ちゃんのこと好きになったの?」
「どうだろう」
まさか。拾った女が未練たらたらでいる元恋人だと知ってしまったら、とてもじゃないけどファンになりたい対象には見えない。でも雨谷真奈だって紙の上の伊月美沙を追い回しているのだからひなたさんが何者なのか知っているはずだし、『ひだまりもよう』以外に歩いて行ける店がないこの街でファッション誌をやり取りするのに駅を指定してきたあたり、ある程度察してはいるのだろう。
少しして、雨谷真奈はぽつりと言った。
「この前はありがとう。その……香凜ちゃんのこと……」
「思ったことを言ってるだけ」
「そっかぁ、あたりまえなんだね。みっちゃんには」
「……そういうわけじゃないけどね」
わたしは雨谷真奈の頬をふにふにとつまむ。
「あれ、照れてるの? 可愛いねぇ」
なでられて、ちゃんとそう見えているのだと安心する。もう、とわたしが苦笑いすれば、雨谷真奈は心地よさそうにじわりと頬を染めた。
「でも快斗くんくんの気持ちはきっと、難しいよね……」
いつもどおりの弱々しい声に戻ったのを合図に、わたしはそっと目を細める。
「どうしてそう思うの?」
「だって陽向さんたち、両想いでしょう?」
勘違いと誘導尋問。どちらだろう。水分の多い澄んだ目。
「ひなたさん? と誰が?」
「美沙ちゃん」
とぼけてるでしょー、と眉を下げながらも、雨谷真奈は明らかに隠しごとをしているわたしを責めるようなそぶりは見せずにいる。
くるくる回っている衛星が浮かんだ。たとえそれが当たっていたとしても、雪野快斗のいちばんが他人になんてなりそうもない。それに気づかず勝手にかわいそうがるほうが、何もしないより引っかき回す。
黙っていてもらったほうがましなのに。頭を使わず、未知の大人数を引き合いに出した常套句を吐くことしかできないのなら。
「知ってたって内緒だよ、それは」
「だよねぇ。みっちゃん、陽向さんと仲よしだもんね」
ぞわぞわと足元から何かが上がってくる気がして、不要なことを言ってしまわないように唾を飲みこんだ。そのとき、閑散とした待合室に、雨谷真奈のはっきりとした声が響く。
「でも私がそう思うのはね?」
「うん」
「美沙ちゃんは陽向さんといるときがいちばん可愛かったの。いつもはかっこよくて、ほかのお友だちといるときはいっぱいふざけてじゃれ合ってるのに、陽向さんが撮る美沙ちゃんは女の子なの」
生まれたての、目。
いちばんめんどうだ。願望がとどまりも行きすぎもせずに正解のまわりをふらふらとさまようというのは。
わたしが黙ったままでいると、雨谷真奈は慌てた様子で首を横に振った。
「その……何も言わなくていいよ、ごめんなさい……」
プライベートだもんね、という消え入りそうな声は、ところどころつっかえて雨谷真奈の顔をより赤くする。
「私、美沙ちゃんが好きで……」
小動物みたいな瞳がうるうるしはじめるから、なだめるつもりで目の奥を溶かすように見つめる。
「真奈はあんまり自分のことを話してくれないから、嬉しいよ。美沙さんはこんなに想われてしあわせ者だね。快斗も真奈がわかってくれて、支えられてると思うよ」
ひとつひとつ丁寧に差し出せば、力がこめられていた拳はやわらかくなった。声を出そうとして口周りの空気が揺れて、ようやく。
「……みっちゃんはやっぱり、神さまみたいだね」
言った、と思った。少し待ってみる。でも頭のなかに響く鼓動は一定のペースを保ったまま。どうして。どうして何も湧いてこない。目頭が熱くなることもなく、身体を満たすのはじゅわじゅわとぬるい炭酸のような——
「どうかしたの?」
その言葉で我に返る。小さくびくついたわたしの手を、雨谷真奈は迷うように握った。
「いや」
そのひとことを否定と捉えた雨谷真奈が、ほっとした表情を浮かべる。嫌なんだよ、と言えずに、口から空気だけが抜けた。知らない感情。聞いたことはあった。だけど自分が抱くなんて。失うことを恐れているわけではないのだから嫉妬ではなくて、きっともっと、卑しい。
わたしの持っていないもの、のなかに。ほかの何かで埋められないものなんかいままでなかったし、そもそも欠けていることに気づいたもののそれがなんなのかわからない。ただ少なくともわたしはあの人の匂いを思い出すたびにこのぬめりけがにじみ出てくることに気づいていた。視界がぐらつく。
その鼻の頭にくちびるで軽く触れると、雨谷真奈は一瞬目を見ひらくも退きはせずに受け入れた。
うらやましいんだ、わたしは。ひなたさんのことが。
©︎Nanako Otake / Studio AOIKARA