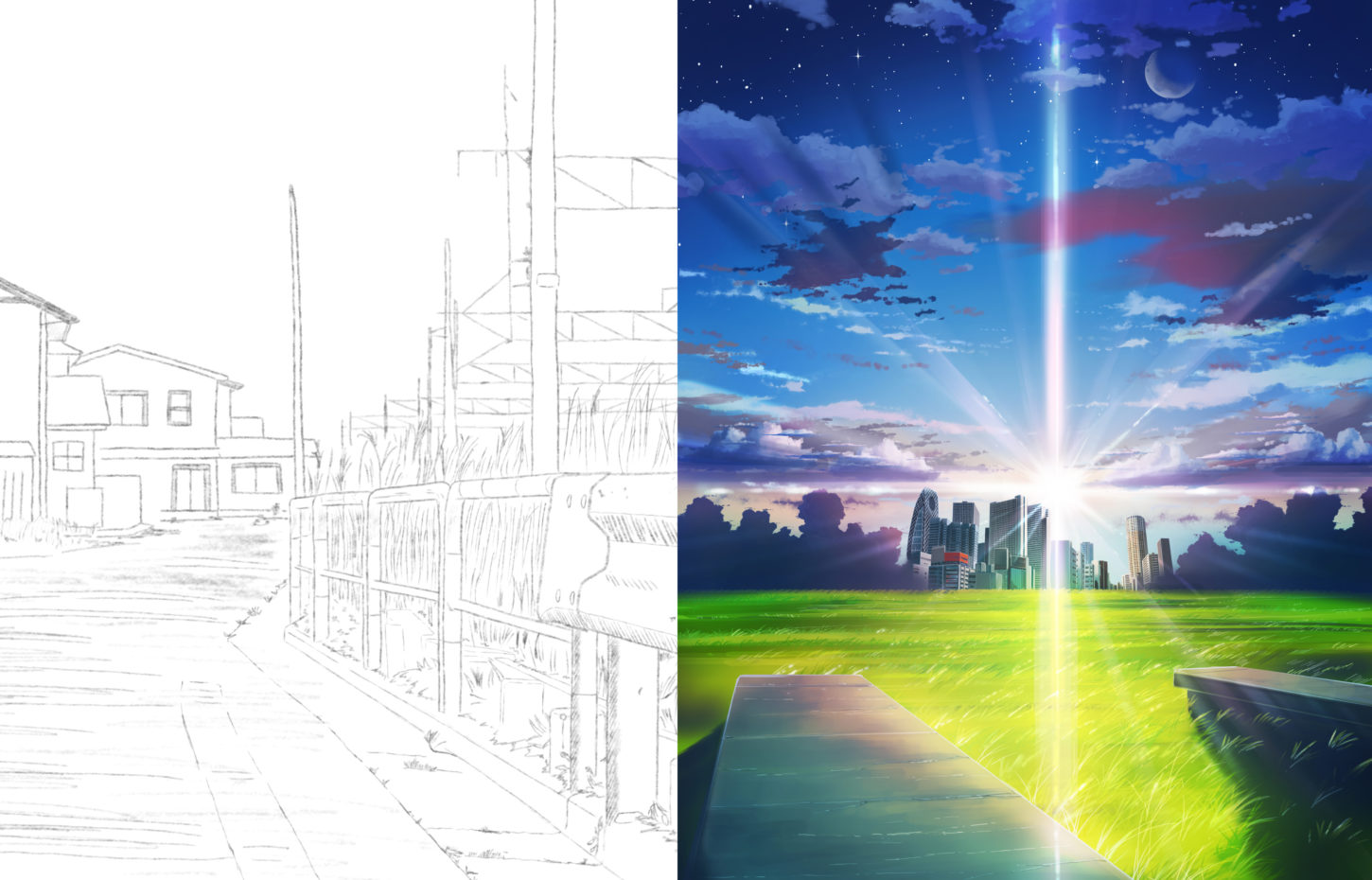第10回 先走って。

4
まつ毛が凍るんじゃないかと思ってしばたくと街はてっぺんまで地続きで、その灰白が徐々に肩の上にたまっていく。それでも空がすり減ることはなく、ペダルを踏むたびにジャージの裾から入りこんでくる肌触りの硬い風も、もはや痛いと思わなかった。
田んぼのなか、高校と中学校が離れて二か所に浮かんでいるのを尻目に、通りに出るとマンションの反対方向に進む。最近までは高校生のたまり場となっているあの店に足を運ぶことはなかったが、「よにんめ」が店の上でひとり暮らしをはじめて親を手伝うようになれば、必然的に行きつけになった。積もりはじめの雪を前輪がしゃくしゃくと押しつぶす。東京で雪が降ると、鎌倉出身の恋人にいちいち知らせていたという。美沙は喜ぶかもって。彼女馬鹿もいいところだ。ほんっと子どもだよね、ときついことを言いながら耳を真っ赤にしている相手も相手だけど。
スピードをゆるめ、両足で地面を蹴りながら店の敷地に到達した。鍵を抜いた手は店に入ったとたん痒くなるのだろうと先走って痺れる。コートのポケットで熱くなっているカイロを握れば、ひりひりと焼けそうになった。
木張りの建物に向かって芝生の間に伸びている砂利道にも、うっすら白い粉が吹いていた。湿っている『ひだまりもよう』の看板を通り過ぎてドアを引く。コーヒーと木の香りで、スニーカーを濡らす雪が、じゅ、と乾く。

ところどころにぽこぽこと吊り下げられた丸い間接照明によって、店内は晴れた日の夕方だった。ダイニングベンチには明らかに定員以上の高校生が密集している。
「おかえり」
やっぱり黒は見慣れないな、と思う。肩下まであったはずの彼女の明るい髪は出会った秋の最初にはすでに短くなっていた。冬が訪れると色も落ち着き、わざとらしくてかてかしているのが妙にいやらしい。
「ただいま」
純来たー、と騒いでいる集団に微笑んでから、いつもあいているいちばん奥の窓際に向かう。マフラーを外して座ったとき、ちょうど目の前に氷だけのグラスが置かれた。その右にアイスティー、左に濃いレモネードが並んで、「遅かったじゃん」という声が降りてくる。
「部活のあと、面談だった」
「そっか、言ってたね」
そんな時期か、と大きな鋭い目が懐かしそうな色に変わった。窮屈でたまらなかった場所を思い出してそんな目をするなんて。どこかでつのったないものねだり。
じゃ、ごゆっくり。とひなたさんは去っていった。エプロン、新しいやつだ、と思いながら、レモネードをグラスに注ぐ。七十/三十でアイスティーを混ぜたとき、あちこちのテーブルから飛んでくる人たちがちらつきはじめる。最初にたどり着いたのは葉山香凜だった。残りに向けては、「あとでぜったいね」と目を細めておく。
「ねぇねぇねぇねぇ!」
「聞こえてますよ。何?」
「ゆっきーにまたお弁当つくるって言ったでしょ? 昨日朝練のときに渡したら今日! プリンくれたの! 心臓止まるほんとヤバい! それで今日もつくったんだけどね——」
専門が決まったら冬休みからマネージャーに復帰していいなんてルールはうちのバスケ部にはなかったように思うのだけど。喉が詰まっているような発し方をしながらもトーンを抑えない甲高い声はよく響く。静かに話すふりをしているだけだ。ここにいる、とは言いたくないから。悲しいことに、彼はだいたい聞いていないのだけど。
反対の隅にいる雪野快斗本人は参考書に夢中でぜんぜん気づいていないものの、少し離れたところでこちらを見ていた雨谷真奈がおずおずしながらうつむいた。
「さっきから『ゆっきー』『ゆっきー』ってさ、オレも一応ゆっきーなんすけど!」
椅子から身を乗り出して絡んでくる双子の片割れ。啓斗うっざい、と葉山香凜に言われても、めげずにわたしのとなりを陣取る。
「またフラれた。純、慰めてー」
「くっつくのは、なしだよ」
もたれかかってくる雪野啓斗を避けるように身体を傾けると、今度は葉山香凜のカフェラテを運んできたひなたさんに泣きついた。
「ひなたぁ、中学卒業してから彼氏いないよなぁ。オレと付き合う?」
またやってんの、と笑う前の戸惑い一瞬。ほんとうはひっぱたいてやりたい雪野啓斗の頭をわたしはふわふわと撫でる。
「ひなたさん、あっちの一年生、オーダーじゃない?」
すなおがすなお。とつぶやく雪野啓斗を尻目に、ふてくされている葉山香凜に呼びかける。ひなたさんは、ほんとだ、と歩いていった。
「なんかやだ、マジで」
身体がものすごい頻度で熱くなっては冷たくなる症状。そのせいで、自分と仲のいい後輩にも相手のおさななじみにもそんな目をするのか。すぐに否定しても苛立ちを増幅させそうだから、うん、うん、と相槌を打つ。カウンター席の一年生の話を聞いているひなたさんは同じように。でも傾けている心は密度ではない何かが違う。左側だけ出ている耳の銀色のピアスが、暖色の照明をきらきらと反射した。
「私も正直気づいてんの、ゆっきーは真奈だって」
葉山香凜の声がしおらしく変わるころには、三、四人がこっちに近づきかけて引き返していた。いつのまにか席を立っていた雪野啓斗は、みんなで冬休みどっか行こーぜ、とせがんでいる。カウンターの奥のひなたさんは嬉しそうな困り顔で、「あーもうわかったから」としみじみ口角を上げた。
「私、真奈のこと嫌いになった」
ゆっきーは黒髪の清純派が好き、と聞きつけて隔絶に悩む彼女は、自分さがしの旅も必要としていそうだった。一人称を発するたびに口元がふらついていて、こっちまで舌ったらずになりそうだ。
「でも真奈は先輩のこと好きですよ」
「好かれたくない。ぶっちゃけさ、ただの後輩だし、優先順位? そんなでもないって」
茶色い前髪を整えて視線を落とす。それを見て、わたしは氷が溶けて若干薄くなった七十/三十を葉山香凜に差し出した。
©︎Nanako Otake / Studio AOIKARA