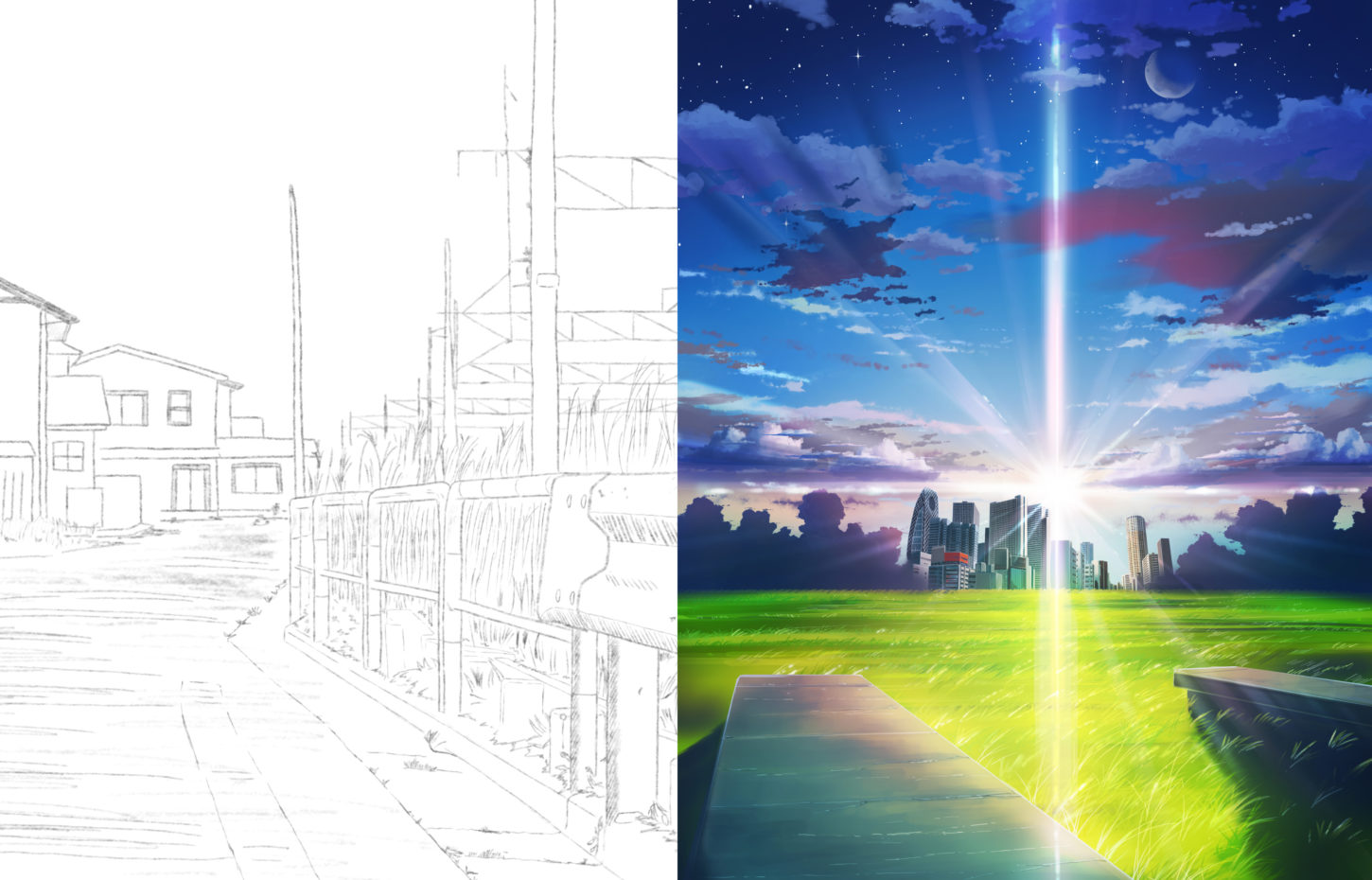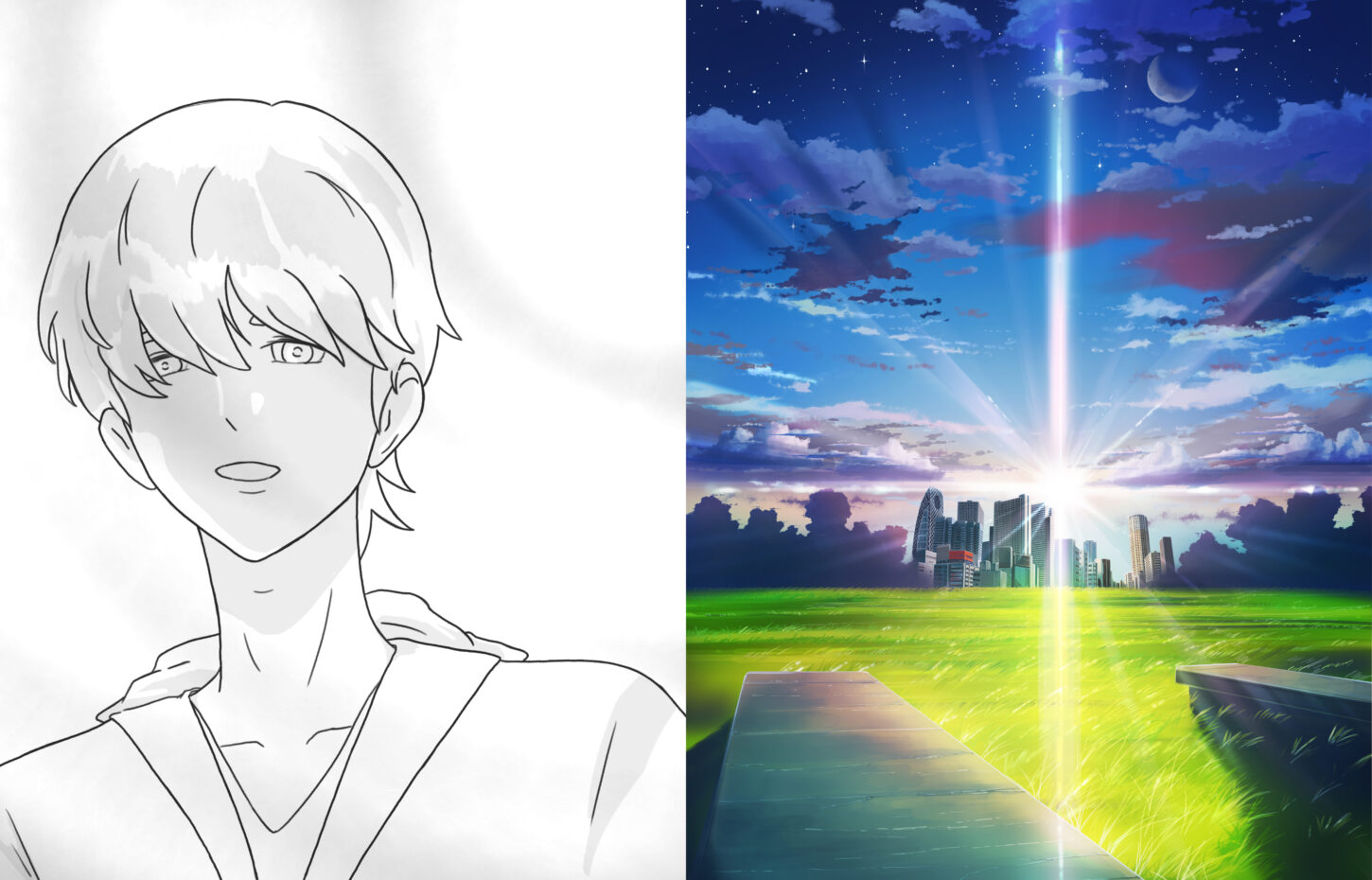第14回 向日葵色。

6
かくれんぼで壁と箪笥の間に挟まれたみたいに、息を吸っても空気が入ってくる気がしない。神経がざわざわと棘を立てているのは淳なのか、それともわたしなのか、という以前に、わたしが淳のなかにいるのかもしれないと思いついてしまってのたうちまわる。生徒会室にスマホを忘れたことに気づき、ブレザーのポケットのなかで、あけたばかりのカイロを乱暴に握りつぶした。
「認証式終わったら顔合わせの前に英語準備室寄るわ。啓斗がオレのノートに自分の名前書いて出しやがったから」
「あぁ、結局終わらなかったんだ」
冬休みは短いってわかっててためるのがわりーんだよ、とぼやく快斗は明らかに苛立っていた。この人は分単位で決めたスケジュールがずれることをひどく嫌う。
「じゃあ先に行って引き継ぎ用の資料出しておくね」
「なぁ、マジでなんで受けなかったんだよ。他薦で会長確実だったろ。なのに書記って、オレに気ぃ遣ってんの?」
その肩書きが彼の人格形成に大いに資するのは知っている。ただ、いまのぬかるんだ心に混ぜてほしくない八つ当たりだった。肺が濡れていく感じがする。
「片方が落ちるより今年も快斗と一緒に生徒会やりたかったんだよ。だいたい、わたしが遠慮しようがしまいがあなたはできる奴でしょ」
「ジュンが言うんだから、まぁそうなんだろうな……」
かみ終えたガムのような味気なさが、なかなかシャッターを切ってもらえないときと同じ気持ちにさせた。もともと始業式はばっくれるつもりではあったけれど、足がもぞもぞと急かしてくる。
「ケータイ忘れたから取ってくるね。先に行ってて」
おう、と頷く快斗にこれでもかというくらい目尻を下げて笑いかけ、ワックスが剥がれそうなほどに床をこすりながら置いていく。いったいこの先どれだけ、意味があると言い聞かせ続ければいいのだろう。そう思ってしまったら、ここはもう電波の入らない地下鉄と変わらなかった。
生徒会室の扉をひらくと、つやつやの黒髪を翻しながら振り返ったのは真奈だった。なぜこんなところにいるのかということはさほど問題に感じられず、りんごの果肉のような白い頬がふわっとゆるむところにこれほど瞳を凝らしたことがあっただろうかと、頭のなかが余計にぼんやりする。
「スマホ置いてあったよ」
「そうそう、ありがとう」
わたしが手を出すと、当然のごとくその上に乗ってきたひとまわり小さい真奈の右手。絡め取られるように距離が縮まり、わたしのブレザーのポケットにはスマホと一緒に反対の手がするりと収まった。
「あ。あったかい」
いますぐにこの生徒会室を飛び出してしまいたい衝動と、真奈の傾慕するさまを見てみたいという落ち着いた欲求がぶつかり合う。ささくれをちぎるときとおなじびくつきがやってきて目を伏せた。前髪にわたしの息を浴びる真奈の綺麗にアイロンがけされたスカートは、素知らぬ顔で脛に触れてきている。
「勝手に来たら怒られるでしょ」
「ちゃんと点呼してきたもん。みっちゃん、朝教室にいなかったから、ここから直接ステージのほうまで行っちゃうのかと思って」
真奈はくすぐったがるように足元に目をやって深く微笑み、もう一度わたしを見上げた。
「ねぇねぇ、私、偏見とかないし、大丈夫だよ」
そう言われる理由を思い出すのに四秒ほど必要で、その間に勘だけで眉を悲壮な下げ方にする。
「ごめん。この前のは、そういうつもりじゃない」
「いいんだよ? 私もみっちゃんのこと、もっと知りたい」
生あたたかい液体に浸かっているかのようにとろんとした真奈の目は焦点が合っていない。ぬるぬると舐めるように輪郭をなぞられる。
「この真っ白な肌は咲記さんだよね? 目が大きいのもそうかなぁ。形が違うのはお父さん? お父さんに似てるの嫌? 咲記さんもまたお出かけしてるし寂しいでしょ? 私が代わりになんでもしてあげるね」
「へぇ」
直感でしかない。ただこの子をうまく取り扱わなければならない気がした。そうすればわたしはきっと、ひなたさんを羨望する理屈を嗅ぎ出すことができる。
「たとえば何してくれるの?」
「毎日ご飯つくりに行くとか」
「あぁ。お手伝いさんは間に合ってる。自分でできるから」
「みっちゃんが悲しいときはどこにいても会いに行くよ」
「時間を奪ってまで遠くにいる人になんとかしてもらおうとは思わないかなぁ」
つながれていた手を少し強引に離す。すると真奈は口をきゅっと結んで、やわくまばたきをした。
「……真奈のこと好きにしていいよ」
最後が高くなるか弱い女の子らしい声が、雨雲になって鼓膜を圧迫する。わたしは真奈に、ほしがるぎりぎりを与えたり焦らしたりするべきなのだ。圧縮された空気を解放するように、濃度の高いゆるやかな目線を捧げる。
「じゃあ、サボっちゃおっか」
ハンガーからするりと脱がせたコートを真奈にかけると、代わりに薄く張っていた憂いが滑り落ちて、ドライアイスのように昇華した。
「みんなの前でお話するんじゃないの?」
「認証の前に戻ってくれば大丈夫だよ。整列と始業式だけで一時間はかかるし」
わかった、と真奈は澄んだ瞳でぼうっとわたしを追いかける。生徒会室の扉がしまるぴしっという音も、体育館に向かう生徒が溢れる廊下の喧騒も、まったく気に留めていないようだった。成分が違う空気が流れているのだ。この子のなかだけに。
通学路に出てわたしが車道側を選ぶと、袖にわずかな重みを感じる。応えることなく歩き続けて校舎の鈍色がわからなくなったころ、真奈が口をひらいた。
「意外と悪い子なんだね」
「そう思う?」
「ケータイの電源は切ってるのに、こんなことするんだぁって」
「真奈の前でだけだよ」
生まれたまま。手ぶらでいるだけ。
少し残念な気持ちになった。
すべての音を奪うように佇む入母屋の本堂まで行かずに、わたしは境内の手前にある登り口の前で足を止めた。
「みっちゃん、登るの?」
「やめておこうか」
「ううん、行きたいんでしょう? 雪もなさそうだし、大丈夫じゃないかな」
真奈の手が降りてきて小指にしっとりと当たる。小さくもたしかに期待が生じてしまったら、それは綿毛のかたまりが浮き立つような熱を帯びるらしかった。
わたしは真奈のてのひらを握りこんだ。
「真奈。滑るかもしれないから、離さないで」
湿っぽくしか鳴かない枯れ葉にむずがゆさを覚えながら、東側を回るように進む。木々の狭間からくすんだ寒さが少しずつ落ちてきて十分ほど歩くと、視界がひらけて白い靄の匂いがした。
かさついている枝が影を落として、苔の生えた亀の甲羅のような模様を地面に描いている。わたしと真奈は不自然に新しい案内板を素通りし、落ちていたビールケースに並んで座った。広がる光景のはんぶんは丸裸で、そこに雲が低くまぶされる。
「よく来るの?」
「ううん、ひなたさんがいるときだけ」
寂しさの影が、真奈の眉と眉の間に浮かんだ。
「人が撮れなくなって帰ってきたんだ、ひなたさんは。だから定期的にわたしが実験台になる。いままで一回もシャッター切れたためし、ないんだけどね」
「そうなんだ……」
ひなたさんがいまだにわたしを撮れていないのは、はんぶんはわたしのせいだ。わたしは気をゆるめずに、ひなたさんが撮りたくなるわたしにならずにいる。生みたくなかった。強引に新しい理由をつくって一緒にい続けるような関係を。
「真奈は、そういうことしてるわたしは嫌い?」
へ、と真奈が口を半びらきにしたとき、背後からもうひとつ素っ頓狂な声が飛んできた。
「え、やっぱそうだ。あんたたち何してんの?」
ひと呼吸おいて振り返る。ひなたさんはいつもどおり、この世のありとあらゆる色にコショウをまぶして適当に並べたような、黒のレザーのモッズコートには絶対に合わないもさもさのマフラーをして、その上からカメラをさげていた。
「人生勉強」
そう答えると、おろおろしてわたしたちを見下ろしたのち、揺るがない平気さを繕ってレンズを確認しはじめる。
「補導されないよーにね」
「うん」
頷いたわたしを見て、ひなたさんは「しょうがないなぁ」というような笑みを浮かべた。圧せられるような空気に逆行しようと足に力を入れているくせに、叱られると思うと胸に影が広がって結局生まれたての子鹿のように立ちすくんでいる。大人がどうだとか言っているのは、子どもだけなのだ。
市街のほうに身体を戻したら、何かが粉雪のように頬に当たっているのを感じる。右半身の皮膚がざわざわと逆撫でられて真奈を見ると、眺めているのはカメラを構えて歩き回っているひなたさんの背中だった。それから瞬きひとつの間に動いた瞳がわたしを映す。頼りない恍惚ではない。街を枠に入れて立て続けに鳴るシャッター音は近づいたり遠ざかったりしている。
「……真奈は何がほしいの?」
はしっこの下がった真奈の目が、まばゆいものを覗きこむようにまぶたを震わせた。
「みっちゃんの目が見えなくなったら、みっちゃんの目になりたい。耳が聞こえなくなったら耳になりたい」
相手の顔がぼやけないぎりぎりのところまで。鼻先が触れそうになる。
「心が疲れそうになったら、代わりに私のを使ってほしい」
でも、と口角を上げる真奈の頬は、ずっと色味を増していった。その上を木漏れ陽の斑点がゆらゆら踊る。
「嫌だって言うなら、なんにもいらない。ただいたいの。私はここにいたいの。みっちゃんの手をあたためて、必要なくなったら離せる距離に……」
真奈がへらっと笑う。わたしはこの人と会っているんだ、と思った。これは、ほんとうの真奈だ。だけど、こういうときにどんな気持ちになればいいのかということを、わたしはよく知らない。蛇口が詰まっている。
「だから私は、ぜったいにみっちゃんにはなりたくない」
知らないふりをしようとした。だけど言葉が白く目に見えてしまってそういうわけにはいかない気がする。
かしゃ、と吸い取られるということは、もろく真珠色に照り返したふうに、あたたかく写っているのだろう。

©︎Nanako Otake / Studio AOIKARA