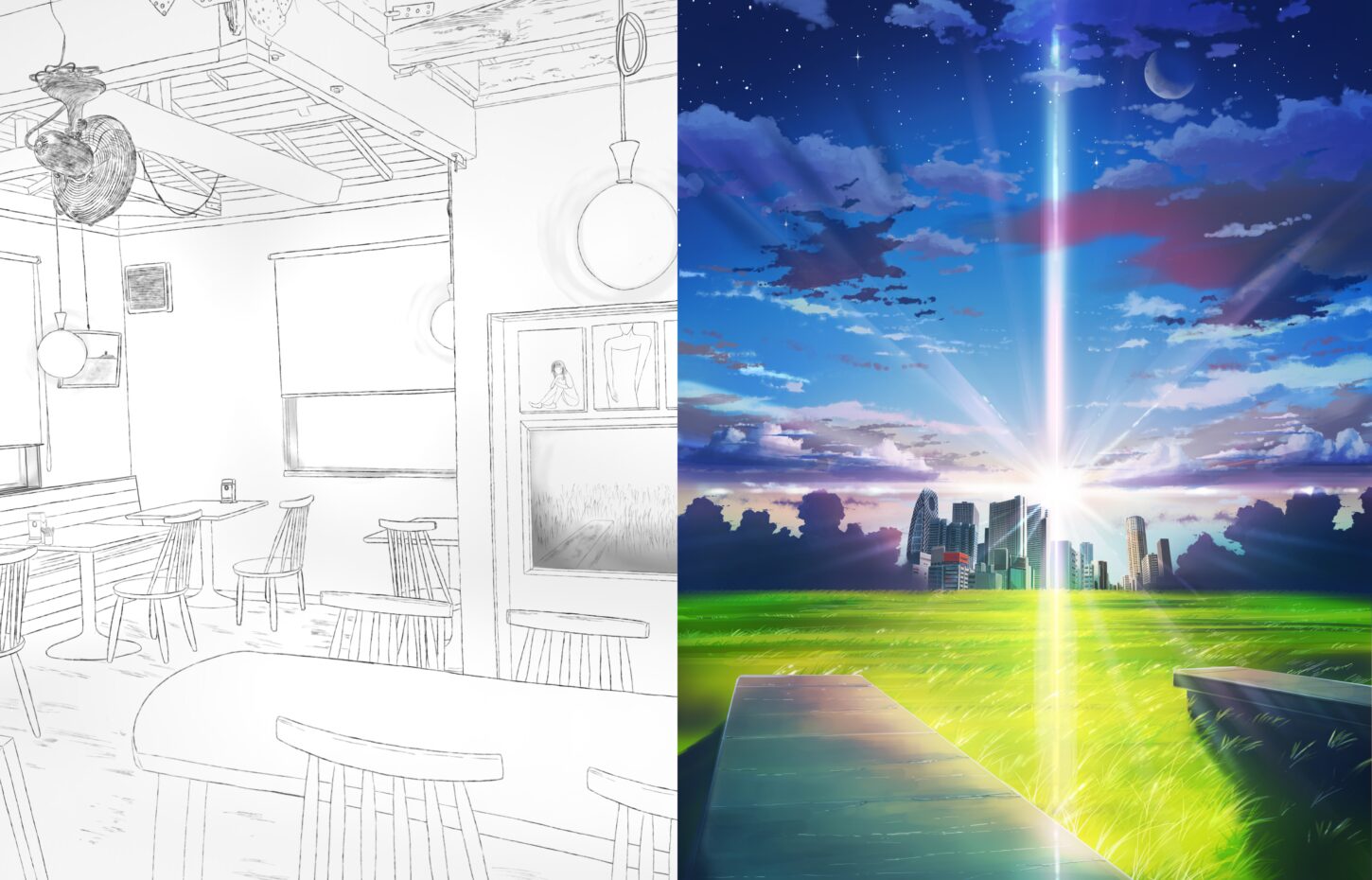第15回 持て余して。

「わかたけいろ」 芳川 陽向
1
理性で歯止めをかけられる半端な大人を持て余して宙ぶらりんが止まんない。
飴色の陽射しがぱらぱらと散る。バイクが硬い叫び声をあげながら海に背を向ければ、もうすぐ4月だった。
起きてからいままでに、小気味よい出来事がいくつもあったはずだった。芝生が汗をかいたみたいにきらきらしていただとか、庭の桜がもうひらきそうだとか、ガレージに押しこんだままほったらかしにしていたバイクを、父さんが定期的にメンテナンスしてくれていたことを知っただとか。
ひとりで風をきるのが日常だった。このG310Rに替えたときも、それまでどおり美沙をうしろに乗せるつもりなんかなかったのだ。なのに黒く光る車体にあまりにも愛嬌のある声を出すもんだから、人生いちの目の渇きを感じるほどしっかり見ひらいて、中目黒のマンションから七里ガ浜まで早朝の湿気を滑っていった。帰りもこんなにいろんな汗を流さなきゃいけないのか、と気が遠くなっているあたしをよそに美沙はにっこにこしていて、はじめてのわがままらしいわがままにおぼろげな気持ちよさが湧いた。その一回しか、美沙はあたしが困るわがままを言ってくれなかった。
映画館のスクリーンのようなメット越しにあの2年半を思い出す。そして、こんなことをするたびに、あたしは老いていくようなのだ。
しまいこむことを諦めてからというもの、頭のなかを煮こまれっぱなしでいるみたいだった。あたしはまるで血の純度が下がったかのように誰にも寄り添わなくなり、気持ちのこもった言葉を使わなくなり、節々に紐をつけられたみたいにあっちへこっちへと引っ張られている。
目のなかまで塗りたくった友だちに、柄じゃない格好、オーバーな表情をした黄色い顔の絵文字、黒髪、ヒール、破れたスニーカー。
あたしはいったいどこへ行った。叫びすぎたぶんだけ、心が息切れしているように思えてならない。なかなか景色が変わらないのも、そのせいだ。
いまだって。純から【今日お店やってるよね?】と連絡があったから早めに切り上げてきたわけじゃない。
大人になると、てきとうになる。自分のなかに通っているものを言葉に変えられるようになる、なんていうのはまやかし。ぜったいに使いたくなかったはずの人様の言葉をちょうどよく捕まえて、お借りしちゃうだけ。
言葉が乱暴なんだよ。言葉遣いが汚いのよりずっと怖いよ、それ。なに言われたって、うそみたいに聞こえるもん。
純もいずれ、いまのままでいることをやめてしまうんだ、と思った。そうすると、近くにいて口をきくだけで二の足を踏んでしまう。周囲が心を動かすごとに、きっと新しい反応を覚えていくんだ。かと言って黙って座っていても時間は流れる。そこにないから懐かしい。
そして、それはもう始まっているように思えた。純はあたしが言葉に詰まると、自分の拙さを小出しにしてくれている。そうしなければあたしが頼れなくなるとわかってるから、あたしがあいつに寄りかかるだけじゃない形をつくり、目線は同じ高さになる。それでも、ずっとどこかで拒まれているような気がしていた。それはあたしをどこまでも食いこませるのに、決して穴のあかない膜だった。
2ヶ月ほど前から、純は過ぎる冬を溶かすみたいに、ときどき何もないような顔で宙を睨む。あたし以外が気づかないらしいその一瞬に何が駆け巡っているの。毎月もらっていくレモンを、あたしは純の部屋で見たことがない。それこそわかってあげなきゃいけないはずなのに、水に足をつけることを怖がる泳げない子のように、いつも瀬戸際で引っこめちゃう。
だから、撮れない。
叫びだしそうなほど揺さぶられる瞬間はいくつも横切るけれど、あたしがとどめをさしたくない。
大人って薄情だよね、と高校生のときによく言っていたけれど、思えばそうなる過程なんて考えたこともない楽天家だった。人でなしは、どっちだよ。
フルフェイスのなかの気体に余分なものが混ざっているような気になって、ごちゃごちゃした緑の木々の間で停止した。ようやく足元に道路を捉える。さっきから何回も、意識のあっちとこっちを行ったり来たりしていた。陽向は死んじゃいそうで怖い、と言う声はたしかに怯えていたなぁ、と思う。そのときのあたしがこじらせすぎていたのか。それともいまになって平坦な道を望んでいるのが正常に気味悪く埋まったこの時代の超え方なのか。余裕で心臓動いてますよと、もし会えるのなら言ってみたい。たとえ白けたまなざしを向けられるとしても。
あー、こんなに考えてたら賢くなっちゃうかも。とか言って、ぶつくさ。独りごとを交えながらあたしは顔を外気にさらし、わあっと息を吸って、鼻から抜いた。首はなんとなく、斜め上に傾けている。少し先のY字路に浮かぶ信号を頼りに、ここにいた。それは緑になって、赤になって、緑になった。大型のトラックはゆるやかに進んで、そのままゴトゴトと越えていった。迷うように速度を変えながら迫ってきた銀色の車は、突然意を決したように黄色信号に突っこんできた。髪の色、戻そうかなぁ。あ、シルバーアッシュも、かっこいいよなぁ。
そうしているうちに、汗は冷たい空気をさまよって、風に消えていった。それからまた走りだし、足首が熱気に晒され、店にたどり着くまで、あたしはあたしだけ。誰も振り返ることなく、無言で横を流れてく。顔面を覆ったまま爆走してるんだからあたりまえか。でももう美沙から離れて1年になるんだ。一緒にいた長さに追いつくまで、あとはんぶんちょい。思い出してほしくないけど、忘れはしないで。
©︎Nanako Otake / Studio AOIKARA