第21回 名称未設定のプレイリスト。

2
そうして電車に乗った。
雨だった。
窓に落ちた水滴が流星のように尾を引く。
県庁所在地の中心駅まで一時間ほどかかるものの、斜めがけに入れてきた文庫本を開く気にはなれなかった。その作者の旧居跡であることを示すプレートがはりつけられていた千代田区のマンションがちらつくからだろうか。今日は別のやつにすればよかったかな、と思う。
だから角の席で仕切りに寄りかかって、左へ左へと進む車両に身を任せていた。イヤフォンから流れ続けている曲に歌詞はない。たいそうなことを語る誰かの声が街中で延々と垂れ流され、消耗品のように扱われるのがわたしにはきまり悪かった。
ふたつめの駅に滑りこむとき、それは名称未設定のプレイリストに切り替わった。ときおり更新されては、タイトルとしてその日いちばんおいしかったものの名前がつく、ひなたさんのスマホのものとおなじ中身。なかば押しつけられるようにあの人の好きな曲を入れ続けていたらこうなった。
しつこくないことばはむしろ心地よく細胞と溶けあう。それはまるで鎮痛剤のよう。なかにいるとあたたかなことばがぽこぽこと出てくる。たとえ朝、雨戸でふさいだ、まっくらに落っこちていても。
がらんとした電車のなか、となりにピンクのスカートを履いた人が座った。
わたしにぺたりとはりついてくるとなりの誰かのすすり泣く声が聞こえてくるのに、顔を上げる気になれなかった。わたしのなかの淳が死んでしまう。ひなたさんに侵食されている。
それでもいま、もうれつに、ひなたさんの匂いのついているものに触れていなきゃならない。
あの人が何を抱えていようと、わたしが思う方向に導いてしまえる、というのはやはり真だった。その気になればあの視界を塗りつぶしてしまうことだってできるのだ。一寸先も見えなくなるくらいに。
そう確かめたにもかかわらず、呼吸は浅いままだった。人混みから離れたいとあれほど思っていたのに、いざ遠ざかったら働かない頭が首の上についているだけだ。いつだろう、清いものに憧れる時期が終わりを迎えたのは。十何年も前に消えたそれを、ひなたさんが奥の引き出しから引っ張り出してしまう。そうしてわたしは、身体ごと生まれたままの大きさにされてしまうのだ。
ひなたさん、最近までこの歌知らなかったんだろうな。
でなきゃ、きっとあのときにしんでた。
となりの人と小指どうしが触れ合った。血管のたくましい手だ。だが爪の裏は青っぽい不気味な色をしている。そこに至るまでにすべてが吸われてしまっているかのように。
距離を取ろうとは思わなかった。だからずっとそのままにしていると、あるとき、来た、と思って腰を軽く浮かした。下腹部が可愛く痙攣して、わたしは終点の駅まで立ち上がらずに朦朧とした意識のなかにいた。
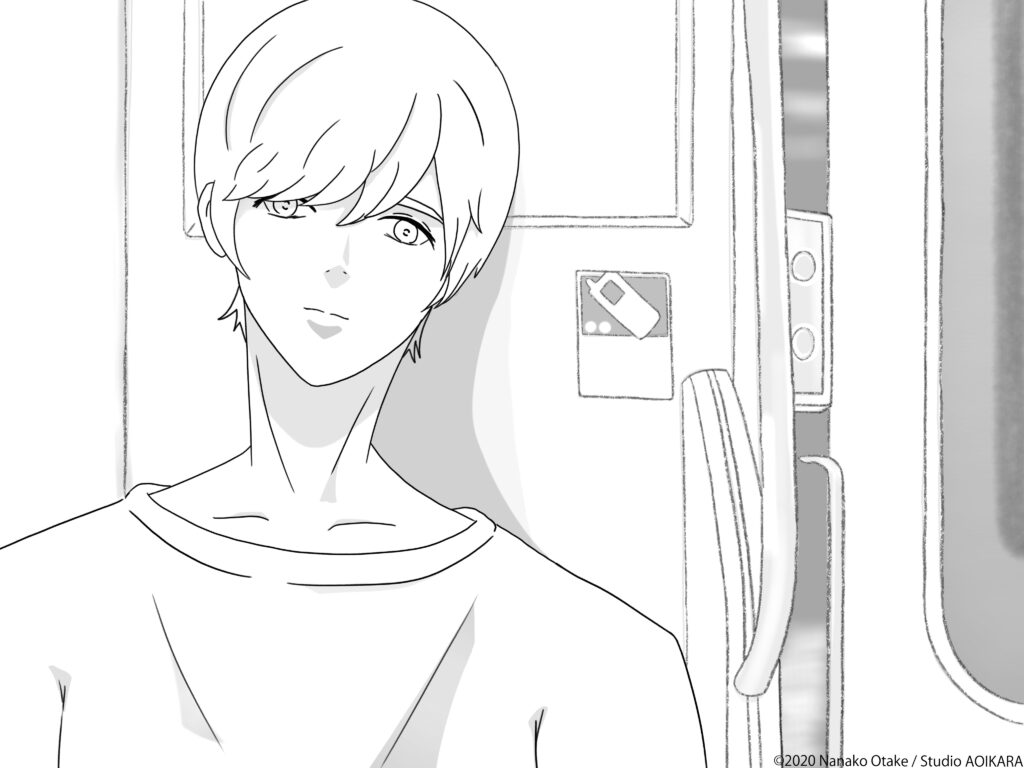
©︎Nanako Otake / Studio AOIKARA




